
早期診断と早期治療が
重要な時代に、
相談先の確認を
筑波大学附属病院認知症疾患医療センター部長
医師 新井 哲明さん
プロフィール
- 1990年4月1日〜1992年8月31日
- 筑波大学附属病院医員(研修医)
- 1992年9月1日〜1994年11月30日
- 医療法人社団有朋会栗田病院医師
- 1994年12月1日〜1996年5月31日
- 東京都立松沢病院精神科医師
- 1996年6月1日〜2010年3月31日
- 東京都精神医学総合研究所主任研究員 (2003年10月1日〜2005年9月30日 カナダ国、ブリティッシュ・コロンビア州立大学医学部精神科キンズメン神経学研究所客員研究員)
- 2010年4月1日〜2012年3月31日
- 筑波大学大学院人間総合科学研究科講師
- 2012年4月1日〜2016年2月29日
- 筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学准教授
- 2016年3月1日〜2022年3月31日
- 筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学教授 兼
筑波大学附属病院認知症疾患医療センター部長 - 2022年4月1日〜現在
- 筑波大学人間総合科学学術院長 兼
筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学教授 兼
筑波大学附属病院認知症疾患医療センター部長
超高齢社会を迎え、認知症とともに生きる将来を誰もが考える時代となりました。近年は、日常生活に支障のないものの軽度な認知機能障害がある段階での治療ができるようになり、早期診断と早期治療の重要性が増しています。
治療の選択肢が増えた一方で、相談先の周知や働く世代で認知症の人への支援など課題も残ります。認知症とともに生きる将来を見据え、早期対応のためにどんなことに注意すれば良いのか、困ったときにはどこへ相談すれば良いのか、第一線で治療にあたる専門家に聞きました。
認知症の原因は100以上、アルツハイマー病が5〜6割
認知症はもの忘れや記憶、空間の認識、言語といった認知機能が低下することで日常生活に支障が出る状態の総称です。
認知症という一つの病気があるというのは誤解で、原因となる病気が100以上あります。一番多い原因はアルツハイマー病で、認知症患者の5〜6割を占めます。アルツハイマー病が原因となるアルツハイマー型認知症の場合は、もの忘れの症状から始まります。
もの忘れより先に、意欲の低下が見られる認知症もあります。
レビー小体型認知症は幻覚や睡眠時の異常行動が特徴。前頭側頭型認知症はもの忘れがあまりなく、感情を抑制ができなかったり、自分の思った通りに行動してしまったりします。また、脳梗塞や脳出血の後遺症として発症する血管性認知症もあります。

【4大認知症】
認知症の主な種類は、①アルツハイマー型認知症②レビー小体型認知症③前頭側頭型認知症④血管性認知症の4種類があり、これを4大認知症と言います。4大認知症で、認知症患者全体の8割を占めます。
4大認知症のほか、甲状腺機能低下症やビタミンB1不足といった体の病気が原因となる認知症もあり、このような場合は原因疾患の治療により症状が回復します。
-

①アルツハイマー型
認知症 -

②レビー小体型
認知症 -

③前頭側頭型認知症
-

④血管性認知症
軽いもの忘れの段階で注意を
日常生活に支障のない軽いもの忘れにも注意が必要です。
日常生活に支障のない加齢によるもの忘れがある方々を追跡した研究で、1年で約1割、5年で約5割が認知症に移行していることがわかりました。日常生活に支障のない軽いもの忘れがある方をMCI(軽度認知障害)と言い、MCIの中に認知症の前段階の方たちが含まれていることが分かってきました。つまり、MCIの段階で治療や進行を遅らせる対策をとることが重要です。
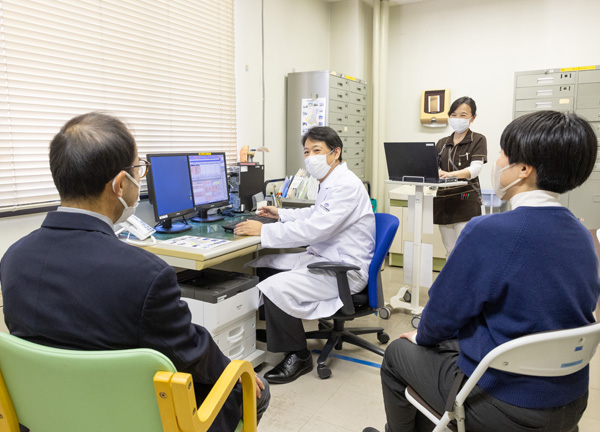
【MCI(軽度認知障害)】
MCI(Mild Cognitive Impairment=軽度認知障害)とは、認知症と完全に診断される一歩手前の状態で、認知症と健常な状態の「中間のような状態」です。
MCIの人は、本人や家族に認知機能の低下の自覚があるものの、日常生活は問題なく送ることができている状態です。

新薬登場で早期診断・早期治療の時代へ
アルツハイマー型認知症治療は今、新薬の登場で大きな転換点にあります。
今までMCIと診断されたら、多くの場合では「様子を見ましょう」と言われるだけでした。しかし、2024年秋にアルツハイマー型認知症のMCIの段階から治療できる新薬(抗アミロイドβ抗体薬)が保険適用になりました。アルツハイマー型認知症の脳の病理に直接作用し、効果を発揮する初めての薬で、早期の段階から治療が可能になりました。
「早期診断・早期治療」が重要な時代になってきたのです。
ただ、この薬は認知症がある程度進んでしまうと投与対象外となってしまうので、注意が必要です。また、精密検査を経て条件をクリアしなければ投与対象とならないため、実際の投与に至る方は希望された方の3、4割程度と言われています。このほか、副作用が出ていないかどうか何回もMRIで確認する必要があるほか、2週間に1回の点滴を行うため、治療を受けられる医療機関が限られています。
MCIの方を対象に認知症の進行を遅らせるため、運動や芸術活動、脳トレを組み合わせたプログラムを展開している病院が県内にいつくもあります。茨城県では、そういった病院を紹介したり、チラシなどで広報活動を行ったりして情報提供ができる体制づくりを進めています。
また、新薬を投与できる医療機関や新薬を認知症のどの段階で投与できるかリスト化した情報をウェブサイトで公開しています。まずは県のウェブサイトをご確認ください。

【抗アミロイドβ抗体薬】
アルツハイマー病の進行を遅らせる働きがある新薬です。抗アミロイドβ抗体療法の投与対象はMCIから軽度の認知症です。
日本では「レカネマブ」と「ドナネマブ」の2種類が販売開始しました。

日常の異変に注意し早期診断へ
このように、認知症治療では早期診断が非常に重要です。
適切なタイミングで治療や生活指導につなげることができれば、認知症の進行を遅らせられるだけでなく、ご家族の負担軽減もできる可能性があります。
早期診断のためにはまず、ご本人やご家族がいかに異変に気がつくかが大切です。
探し物が多くなった、忘れてしまうことが増えたということは気がつくポイントになります。また、今までできていた家事や趣味をあまりやらなくなった、やる気がなくなったという症状も認知症の始まりであることがあります。まずそういう異変に注意しましょう。
異変に気がついたら、専門機関に相談してください。
相談先としては「地域包括支援センター」「認知症疾患医療センター」が専門機関ですので、ぜひ相談していただきたいです。
また、かかりつけ医がいれば、その先生から専門機関を紹介してもらえます。かかりつけ医の先生方も認知症に関する研修を受けていて、適切に提供できる先生が増えています。気軽な相談先という意味でも、かかりつけ医を持つことは大切です。

【認知症疾患医療センター】
認知症の医療やケアを専門とする経験豊富な医師や精神保健福祉士など、多職種が在籍しています。茨城県は各二次医療圏に一箇所、医療と介護、その他の地域の社会資源をつなぐ役割を果たす医療機関を指定。この臨床疾患医療センターには、 臨床の専門医が必ず1名以上と専門の相談医がおり、認知症の鑑別診断や初期診断、医療的ケアを行います。認知症の初期から進行期まで、患者のそのときの問題に対応します。

安心感得られる暮らしや環境づくりを
認知症になったら「全ての脳の機能がダメになってしまう」「人間として終わってしまう」というような誤解がありますが、全部の脳領域が侵されるわけではありません。残っている機能を活性化していくことで日常生活を続けることができます。また、薬物療法や非薬物療法などで進行を遅らせられたり、良くなったりする場合もあります。
また、認知症が進行しても、ご本人の気持ちを尊重する対話が必要になります。自尊心が傷つけられたり、不安を煽ったりする対応が続くと、認知機能の低下だけでなく幻覚や妄想、徘徊、怒りっぽくなるなどといったBPSD(行動・心理症状)が出やすくなります。そうすると、介護をする側の負担が大きくなるだけでなく、認知症も進みやすくなります。
ご本人が安心できる対応をすることで、ご家族の安心も得られると思います。
このため、ご家族にいつもお話しているのは①怒らない②間違いを指摘しない③できることに着目する④やってくれたことに感謝するという4つの原則です。
「指摘した方が認知症が進まないのではないか」「苦手なことも頑張ってやらせた方が良いのではないか」という誤解がよくあります。しかし、感情が安定していることが大切ですので、本人のできないことを手助けしながら、最終的には本人が上手くできたという風にする方が良いと思います。また、ご本人が安心していられるような環境をご家族だけでなく、社会全体で作っていくことが大切ではないでしょうか。

「空白の期間」埋め、本人と家族に寄り添うシステムを
課題となっているのは、認知症と診断されてから支援にたどり着くまでの「空白の期間」と、異常を感じてから正確な診断を得られるまでの「空白の期間」。どちらも平均で1年から1年半と言われていますが、その間に認知症の進行やBPSDを発症してしまったり、ご本人やご家族が絶望してしまったりと色々なことが起こります。このため、いかにこの「空白の期間」をなくしていくかが求められています。
「周りに知られたくない」「恥ずかしい」といった理由で、医療機関を受診するまでに時間がかかることがあります。特に若年の方でこのケースが目立つように思います。ご本人たちが心配なときや困ったとき、いかに情報を得やすい環境を整えるか。診断後に病気について伝えるだけでなく、その後の支援などについてもきちんと情報提供し、寄り添う体制をとっていくことが重要だと思います。
これから早期の方が来られて診断を受けるという時代になるわけですが、そうしますと就労支援をどうしていくのかや活躍の機会づくりといった課題があります。また、早期の方は、中等症の認知症の方々が利用するデイサービスでは居場所を感じられない場合もあります。このほか、非薬物療法をどこでも受けられる体制づくりも必要です。これは新薬の対象にならなかった方やMCIと診断されなかった方にも提供できるものとして非常に重要です。
認知症初期から進行期まで切れ目なくご本人と家族に伴走していけるシステムをつくり「空白の期間」をなくしていく。そのためにも認知症疾患医療センターの役割は大きいのではないかと思っています。

左:医師 新井 哲明さん
右:精神保健福祉士 江湖山 さおりさん
左:医師 新井 哲明さん
右:精神保健福祉士 江湖山 さおりさん
【医師とコメディカルの連携】
認知症疾患医療センターでは、認知症の鑑別診断や治療を行う医師を中心に、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理師、リハビリテーション専門職等、多職種が連携して、認知症の人の診療とケアにあたっています。
たとえば、看護師は、認知症の人が安心して治療が受けられるよう診療や療養上のサポートを行います。臨床心理師は、認知機能に関する検査や心理面に配慮した面談を行います。精神保健福祉士・社会福祉士は、認知症が疑われる段階から、認知症の本人と家族が抱える不安や心配事の相談にのり、受診のサポートや必要な情報を提供します。また、認知症と診断された後も、地域で安心して生活が継続できるよう、行政や地域包括支援センター等、地域の関係機関と連携しながら、認知症の本人と家族に対して継続した支援を行います。言語聴覚士や作業療法士等のリハビリテーション専門職は、認知症の人ができるだけ長く自立した生活が送れるよう、言語訓練や日常生活を送るうえでの生活環境についてのアドバイス等を行います。
このように、認知症疾患センターには、認知症の人と家族が安心して地域で暮らしを続けられるよう支援に関わる様々なスタッフが在籍しています。

